こんにちは、オヤジです。
ついに、ステーブルコイン「JPYC」が発行開始されましたね。
引用:Yahoo!ニュースより
国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」発行開始 次世代の“通貨”目指す
日本円と連動した日本初のステーブルコインである「JPYC」の発行が開始された。フィンテックベンチャーのJPYCが金融庁に資金移動業者として登録し、電子決済手段の発行が可能になったため、2025年10月27日に正式にステーブルコインJPYCの発行に至った。
「ステーブルコイン(Stablecoin)」の中でも、日本円に1円=1JPYCとして連動しているのが、JPYC(ジェーピーワイシー)です。
近年は円安やインフレ、利上げといったニュースも増え、
「仮想通貨は気になるけど、値動きが怖い」
「JPYCなら円と同じ価値だから安心なのでは?」
と考える人も少なくありません。
では実際、JPYCを“資産形成の手段”として使う価値はあるのでしょうか?
円と価値が同じ通貨を、わざわざ仮想通貨として持つ意味はあるのか?
結論から言えば、JPYCは「資産を増やす」ための通貨ではなく、資産を“守る・動かす”ためのツールではないかとオヤジは考えています。
この記事では、以下を知りたい方におススメです。
ステーブルコインとJPYCの仕組みを理解しよう
ステーブルコインとは?仮想通貨の“安定型”

ビットコインのような仮想通貨は、価格変動が大きくて怖い――
そう感じる人にとって、「ステーブルコイン(Stablecoin)」は比較的安心できる存在です。
ステーブルコインは、ドルや円などの法定通貨に価値を連動させる仕組みを持つ仮想通貨です。
たとえば「1ドル=1USDT」、「1円=1JPYC」といった形で価格を固定することで、値動きの少ない安定したデジタル資産として利用されています。
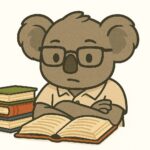
円とJPYCは同じ価値なんですね
JPYCとは?日本円と1対1で連動するステーブルコイン
JPYCは、日本円と1対1で価値が連動するステーブルコインです。
発行元は「JPYC株式会社」で、利用者が日本円を送金すると、その金額に応じてJPYCが発行されます。
JPYCはイーサリアムやPolygonなど複数のブロックチェーンで流通しており、円の価値をデジタルの世界でそのまま扱えるのが最大の特徴です。
JPYCの使い道と信頼性
JPYCは、NFTマーケットやWeb3サービスでの決済、一部の店舗支払い、電子チケット購入などで使えるほか、仮想通貨の中継資産としても活躍します。
引用:Yahoo!ニュースより
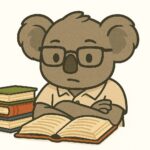
ふるさと納税にもJPYCが利用できるようになるかもです
たとえば相場が不安定なとき、ビットコインをいったんJPYCに換えることで価格変動リスクを避ける――そんな“デジタル避難通貨”としての役割も持ちます。
ただし、JPYCは銀行預金のような元本保証があるわけではなく、法整備もまだ途上です。
今後使い道も増えて便利になってくる可能性も十分考えられますが、「便利だけど、リスクゼロではない」ことを理解した上で利用する必要が大切ではないでしょうか。
資産形成でJPYCを使うメリットはあるのか?

① 価格変動が少なく、安定して価値を保てる
資産形成において「守りの資産」は欠かせません。
株式や仮想通貨のように価格が大きく上下する資産ばかりを持っていると、短期的な値動きでストレスを感じる人も多いはずです。
その点、JPYCは1円=1JPYCとして価値が固定されているため、市場の変動に影響を受けにくく、「デジタル上の現金」的な役割を果たせます。
仮想通貨を売却してJPYCに換えておけば、暴落局面で資産価値を一時的に保つことが可能です。
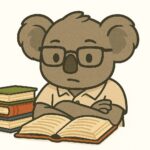
変動が小さいのはメンタル的に安定しそうですね
② 仮想通貨間の中継資産として便利
仮想通貨の世界では、「BTC→USDT→ETH」といった形で、異なる通貨間の取引を行う際に“中継役”が必要になります。
JPYCも同様に、円建ての中継資産として使える点がメリットです。
たとえば「日本円で仮想通貨を買いたいが、一時的に現金化せず保管したい」場合、JPYCに変えておくことで税務処理や送金の効率を高められます。
特に円安が進む局面では、「円ベースで価値を固定したい」という需要が生まれやすく、JPYCがその受け皿になります。
③ 手数料が安く、送金が速い
JPYCはブロックチェーン上で取引が完結するため、銀行を経由するよりも手数料が圧倒的に安く、送金スピードも数分〜数十秒レベルです。
国内外への送金や、Web3サービスでの利用では非常に効率的です。
「資産形成=お金を増やす」だけでなく、“お金を動かすコストを下げる”ことも広義の資産形成と言えると思います。
この点でJPYCは、他の金融手段にはない強みがあると言えるかもしれませんね。
まとめ:JPYCのメリットは“運用よりも効率性”
JPYCは、値上がり益を狙う資産ではありませんが、「守る・動かす・効率化する」ためのデジタル円として活用できます。
資産形成を“増やす”だけでなく、“管理・移動・保全”までを含めたトータル戦略で考えると、JPYCの位置づけが見えてきます。
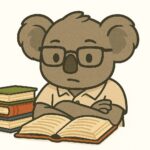
「運用するための資産」ではなさそうですね
JPYCのデメリットと限界を理解する

① 値上がりしない=資産が増えない
繰り返しになりますが、JPYCは常に1円=1JPYCとして設計されていることから、価格が上がることはありません。
つまり、値上がり益(キャピタルゲイン)を狙うことができないのです。
そのため、株式や投資信託、NISAなどのように「リターンを得る目的」で保有する資産とは根本的に性質が異なります。
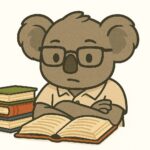
値上がりを目的に持つものではないですね
② 円に戻すときの手数料・スプレッド
JPYCは「日本円に戻す=換金」するときに、手数料やスプレッド(交換コスト)が発生します。
国内外に送金する場合に銀行を経由するよりは「比較的安い手数料」で送金できることは上述しました。
とはいえ、「手数料がかかる」。
つまり、「円と同じ価値」ではあっても、実際に現金化するまでにコストがかかる点は無視できません。
特に短期間で頻繁に入出金する場合、そのコストが積み重なることで、実質的な価値を押し下げるリスクがあります。
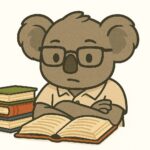
多かれ少なかれ手数料は資産形成の天敵
③ 長期保有には不向き(インフレ耐性がない)
もう一つの注意点は、インフレに弱いことです。
JPYCはあくまで「1JPYC=1円」なので、日本円の購買力が下がれば、JPYCの価値も同様に下がります。
たとえば、物価が上昇して円の価値が実質的に下がった場合、JPYCを長期で持っていても「資産が目減りする」のと同じです。
この点で、JPYCは「お金を動かすには便利」でも、「お金を守る・増やす」には向いていない資産と考えてよいのではないでしょうか。
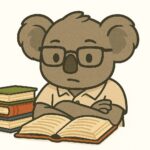
低金利の円預金がインフレ負けするのと同じです
まとめ:JPYCは“メイン資産”にはなりにくい
JPYCはあくまで流動性を高める補助ツールです。
「円と同じ価値を維持できる=安全」ではなく、増えない・手数料がかかる・法的に不安定という弱点もあります。
したがって、資産形成のメインには向かず、株式・投資信託・債券などと組み合わせて使う“サブ資産”として位置づけるのが現実的です。
結論:資産形成目的で“持つ”必要は今のところない
オヤジの結論はシンプル。
JPYCは、資産形成の手段として「オヤジは今は持たない」です。
確かに「ブロックチェーン上で使える日本円」という点は面白い。ただ、資産形成の観点で見れば、
- 値上がり益は期待できない(=円と同じ)
- 銀行より高い利息もない
- 手数料がかかる
- インフレ負けする
この4点で、“リスクと手間の割にリターンがない” というのが正直なところです。
もし資産運用を考えるなら、同じ円を使って 高配当株や投資信託を積み立てた方が、よほど合理的 だと考えました。
オヤジの資産形成の目的はこちらの記事をご覧ください。
JPYCは、将来のために「体験しておく程度」で十分で“持たない判断も、立派な投資判断” です。
みなさんはどう考えますか?

では、今日はこのへんで。また寄ってって
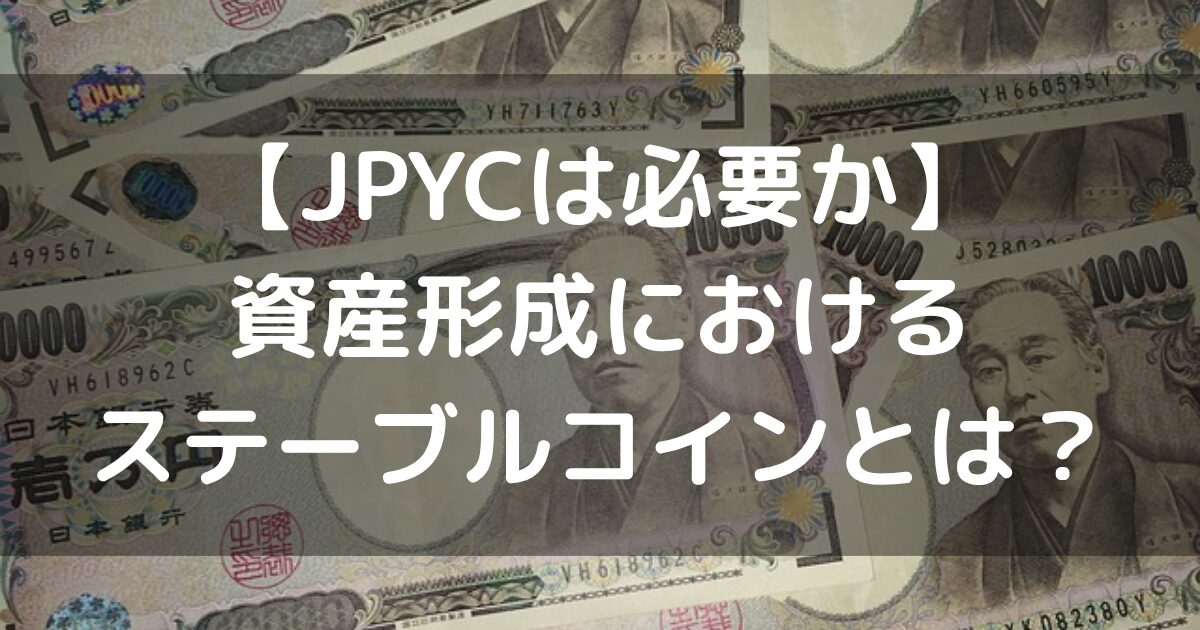
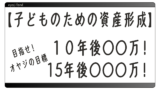
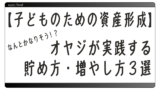
コメント